みなさんのお子さんは、ごっこ遊びが好きですか?
わが家の3歳の娘はごっこ遊びが大好きで、隙あらばごっこ遊びを始めます。
頑張って娘の相手をする私ですが、独特な世界観で繰り広げられるごっこ遊びは正直しんどい……苦痛です。
このままでは私も娘もかわいそうだと思い、この状況を打破すべく、私は工夫を重ねてきました。
そして、ごっこ遊びのしんどさを軽減するコツを見つけたのです。
この記事では元小学校教員の私が見つけた「ごっこ遊びを乗り切るためのコツ」を5つご紹介していきます。
子どもとのごっこ遊びに悩むママ・パパの参考になれば嬉しいです。
ごっこ遊びが「しんどい」3つの理由

ごっこ遊びをしんどいと感じるママ・パパの声は意外にも散見されますし、私のママ友界隈でもごっこ遊びを可能な限り避けているというママが多いです。
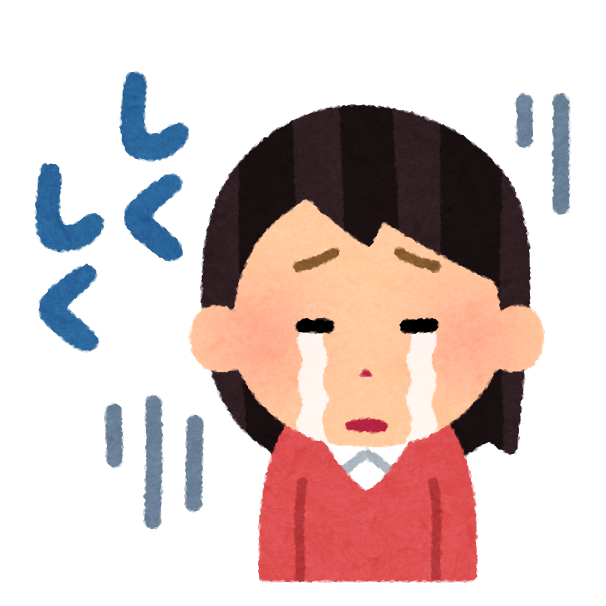
4歳のごっこ遊びに付き合うのが本当に辛いのだけどどうしたらいいの。あれこれ理由つけて回避してる… 引用:X
ごっこ遊びが疲れる理由の意見を集めてみると、以下のような共通点があることがわかりました。
- いつも同じ流れがずっと繰り返されるから
- 子どもの遊びにずっと付き合う必要があるから
- 独特な子どもの世界観に付いていけないから
どの意見を見ても「わかる、わかる!」と大きく頷いてしまいます。
以下でごっこ遊びがしんどい理由を詳しくご紹介しますので、「辛いのは自分だけじゃないんだ!」とご自身を肯定するのに役立てていただけたら嬉しいです。
1つずつ確認していきましょう!
ごっこ遊びがしんどい理由①:いつも同じ流れがずっと繰り返されるから



息子の登園拒否により月曜日からほぼ軟禁生活…3歳とのエンドレスごっこ遊び辛いよ 引用:x
ごっこ遊びがしんどい理由として真っ先に思いつくのは、同じような内容のストーリーを毎日繰り返し演じる必要がある点です。
ごっこ遊びは「お母さんごっこ」「戦いごっこ」などパターンが限られていますし、お子さんによってはお気に入りの内容をひたすら繰り返す場合も。
最初の1回はなんとか全力で対応できても、代り映えのない内容を反復することに正直ウンザリする親御さんが多いのではないでしょうか。
同じ流れの繰り返し……これがごっこ遊びに付き合うのがしんどい理由の1つです。
ごっこ遊びがしんどい理由②:子どもの遊びにずっと付き合う必要があるから



一人遊びができなさすぎる。遊び方もひたすら謎設定のごっこ遊びで辛い。 ※引用:X
ごっこ遊びをしている間大人は絶えず子どもの隣で相手をする必要があり、それにストレスを感じる場合があります。
例えば子どもがパズルやブロックで遊んでいてくれれば、大人はその場を離れて家事をしたりホッと一息ついたりできますよね。
しかしごっこ遊びにおいてブレイクタイムは決して許されません。
子どもの気が済むまで拘束される……ママやパパがしんどくなるのは当然ですね。
ごっこ遊びがしんどい理由③:独特な子どもの世界観に付いていけないから



息子とのごっこ遊びがほんっとーーに苦痛だ…設定など分からない中、息子の怒りスイッチに触れないように探り探りやるのが本当に辛い。うっかり間違えると(間違いとは?)、怒っていじける。マジ難易度高ぇぇぇ。。 引用:x
ごっこ遊びの「設定」には子どもなりの世界観やストーリーが反映されており、その世界に入って演じるのが苦痛というママの意見がありました。
理解が難しいストーリーを永遠に演じさせられるのは、大人にとってはしんどいですよね。
加えてお子さんによっては、ママやパパが自分の想像するストーリーと異なる発言をすると、気分を乱し癇癪を起こす場合もあります。(わが子もこのタイプです)
「早く終わらないかな~」との心の声を必死に抑えながら、子どものためにごっこ遊びに付き合うママ・パパは本当に偉大です!
ごっこ遊びは何のため?ごっこ遊びで身に付く5つの力


大人にとっては忍耐力が伴い、「しんどい」と感じるごっこ遊び。
実はごっこ遊びは子どもの成長において欠かせない力を育んでくれる優れた遊びです。
具体的には、ごっこ遊びでは以下の5つの力を育ててくれます。
ごっこ遊びの価値を知れば、子どものごっこ遊びに付き合う私たちのモチベーションも上がるかもしれません。
以下でご紹介しますので、確認していきましょう!
想像力・創造力
ごっこ遊びで身に付く代表的な力は「想像力・創造力」です。
ごっこ遊びを定義するときに「想像遊び」との言葉を用いることがありますが、ごっこ遊びは「想像力」を使って、自由に世界を「創造」する遊びです。
そのため、ごっこ遊びを継続すれば、自然と「想像力・創造力」が鍛えられるのです。
ごっこ遊びはごっこ遊びは子ども時代の遊びのなかで、想像力がもっとも豊かに、活発に使用される遊びであり、想像力そのものがその活動のなかで、発達していくのである。
※引用:幼児のごっこ遊びの想像力について
想像力・創造力は、良好な人間関係を築く土台であり、困難を乗り越える力になります。
子どものころから想像力・創造力を養うことは、子ども時代はもちろん、大人になってからも理想的な人生を送るうえで大切と言えるでしょう。
ごっこ遊びで、自然と人生の基盤となる力を伸ばしているのです。
表現力
2つ目にご紹介するのは「表現力」です。
ごっこ遊びは自分が演じる役柄になりきって、日常で起きた出来事やアニメの世界などを想像し、表現する遊びです。
子どもは自分が思い描く世界を表現するために、言葉や身振り・手振りなどを使って創意工夫を重ねるため、ごっこ遊びをすれば自然と表現力が培われるのです。
またお友達や大人と一緒にごっこ遊びをすれば、自分の表現の幅を広げることにも繋がります。
表現力が重要な理由
表現力は、他者との良好な人間関係を築くために大切です。
自分の考えを相手に伝えたり、相手の考えを聞いたりする力や、人間関係を築いていく力を身に付けにくくなっていると言われている。(中略)「自ら考えたことを豊かに表現し、他者と相互に考えることができる力」を育成する必要があると考える。
※引用:豊かな表現力を身に付け、主体的に学び合う子どもの育成~「比較すること」を取り入れた学習指導をとおして~
ごっこ遊びの中で失敗しながら表現を続けていく過程で、子どもは表現力の基礎を培い、やがて豊かな人間形成に繋がっていきます。
社会性
ごっこ遊びでは、ルールや順番を守るといった「社会性」を身に付けられます。
- ごっこ遊びの内容には日常生活が反映される場合が多く、「規則を守る」など社会性あるごっこ遊びをする場合がある
- 友だちとのごっこ遊びでは、「譲る」「協調する」などのやり取りを通して社会性が養われる
- ごっこ遊びに大人がサポートで入ることで、適切な振る舞い方を学べる
私自身、ごっこ遊びの中で「ただいま社会性づくり中」と意識することで、ごっこ遊びのモチベーションを保っています。
たとえば、娘はよく「けんかをする」というシチュエーションのごっこ遊びをしたがります。
そこで、娘が相手役(私)のおもちゃを取り上げようとしたとき、「やめて」「私のだよ」などと被害を受ける人の気持ちを伝えるようにしています。
以前は「なんでわざわざ喧嘩するごっこ遊びなんてしなきゃいけないんだ」と感じ、娘は性格が悪いのかと心配していたんですけどね(笑)
実際、娘自身も、「ごっこ遊びを通して現実世界で起きている事象を理解しよう」と努力しているのかもしれませんね。
コミュニケーション能力
ごっこ遊びは「コミュニケーション能力」を育む大切な遊びです。
なぜなら、言葉のやり取りを通して話が進む「ごっこ遊び」は、言語的なコミュニケーション能力を鍛えるからです。
自分の気持ちを伝えるためや、物語を進めるうえでの発言はもちろん、自分の意図と違う内容を相手が発したときの対応など。
実は、ごっこ遊びは高度なやり取りが必要なのですよね。
思考力
ごっこ遊びでは、思考力や相手の立場になって物事を考える力が養われます。
ごっこ遊びでは、年齢が進むにつれ、自分ではない「誰か」になりきって物語をすすめます。
そのため、他者の気持ちを想像したり、他者の目線で考えたりする力が身に付くのです。
教員時代、「相手の気持ちを考えよう」と口を酸っぱくして言っていた私ですが、ごっこ遊びがその礎になるとは……ごっこ遊び、素晴らしいですね。
しんどい!ごっこ遊びを乗り切るコツ


ごっこ遊びに大きなメリットがあるとはいえ、ごっこ遊びは苦痛……と感じる人がいるのは自然です。
私も、ごっこ遊び中は「はやく終わらないかなあ」と思うことが正直なところ。
そこで、私自身の経験から発見した、ごっこ遊びを乗り切るコツを5つ紹介しようと思います!
私は、上記を実践することで娘とのごっこ遊びが随分楽になったため、みなさんの参考になれば嬉しいです。
終わりの時間を決めてから始める
ごっこ遊びをする際は、あらかじめ終わりの時間を決めて、子どもと共有してから始めるのがおすすめです!
ごっこ遊びって、カードゲームや工作などとは異なり、終わりがありませんよね?
終わりが見えないと親も頑張れませんので、最初に終わりを決めて、子どもに納得させましょう。
- 時間を決める際は、子どもと相談しながら決めよう!
- ごっこ遊び後におこなう楽しい予定を伝えると、なおベター!
- 終わりの時間が近づいたら、そろそろ終わりだよとリマインド
- 時間になったときにキリが悪いならば、キリが良くなるまで付き合おう
親が頑張れる時間を設定すれば、そこまではなんとか気合いをいれて付き合えるかもしれません。
ごっこ遊びをするときは、終わりの時間を決めてしまいましょう。
ごっこ遊び×ほかの遊びで展開
ごっこ遊び×ほかの遊びで展開すると、親の退屈度合いが減るでしょう。
- ごっこ遊びをしながら、粘土遊びをする
- ごっこ遊びをしながら、パズルをする
- ごっこ遊びをしながら、テレビを見る(笑)
- ごっこ遊びをしながら、積み木遊びをする
たとえば、「お母さんごっこ」をしているならば、子どもの面倒を見るという状況を利用して、粘土遊びをするのはどうでしょう。
粘土遊びをするうちに、だんだんと熱が入り、ごっこ遊びよりも粘土遊びに熱中してくれるかもしれません。
そうすれば、親の負担も減りますね。
ごっこ遊びのバリエーションを広げる
ごっこ遊びのバリエーションを広げることも、親の退屈を防ぐには効果的です。
お子さんによるところもありますが、子どもは気に入ったシチュエーションを繰り返しがちではないでしょうか。
私の娘は、まさにそうです。
毎回同じ状況は非常に付き合い難いので、親から積極的に新しいシチュエーションを提案してみましょう。
- アイドルごっこ
- ダンサーごっこ
- お医者さんごっこ
- 入院ごっこ
- レストランごっこ
- お買い物ごっこ
- ねんねごっこ
アイドルごっこは、音楽を流し踊るだけなので、音楽好きの親子にぴったりです。
レストランごっこは、注文をとるところから始めれば、お料理時間中は待機時間になるのでおすすめですよ。
自分の領域にごっこ遊びを巻き込む
ごっこ遊びが苦手なパパ・ママは、自分の好きな領域でごっこ遊びをするとストレスが減ります。
たとえば、料理が好きな人は、ごっこ遊びと称して実際に料理をするのはいかがでしょう?
もしくは、「お掃除ごっこ」と称して、家じゅうをピカピカにするのもおすすめです。
子どもの領域に合わせすぎず、自分が楽しめる領域に子どもを引っ張ってくれば、ストレスフリーでごっこ遊びができるでしょう。
お断りして違う遊びに誘導する
ごっこ遊びを断ることも、立派な選択肢の1つです。
ごっこ遊びはとにかく無理(涙)……そんなパパ、ママも、どうか自分を責めないでください。
ストレスを溜めながら付き合うよりも、遊びを断って違うことをしたって良いと思います。
外に出るのが好きな人は外へ出れば良いし、テレビに頼ったって良い。
大事なのは、パパ、ママが笑顔でいること。
自分を大事にするために子どものお誘いを断ることは、結果的に子どもを大切にすることでもあると思うのです。
まとめ
本記事では、お子さんとのごっこ遊びがしんどい!と悩むパパ・ママに向けて、ごっこ遊びを乗り切るコツを5つ紹介してきました。
ごっこ遊びには、子どもの成長を促すメリットがたくさんあります。
パパ・ママが自分を大切にすることを重視したうえで、できる範囲でお子さんとのごっこ遊びを楽しんでみてください!
みなさん、毎日の育児、本当にお疲れ様です!!!


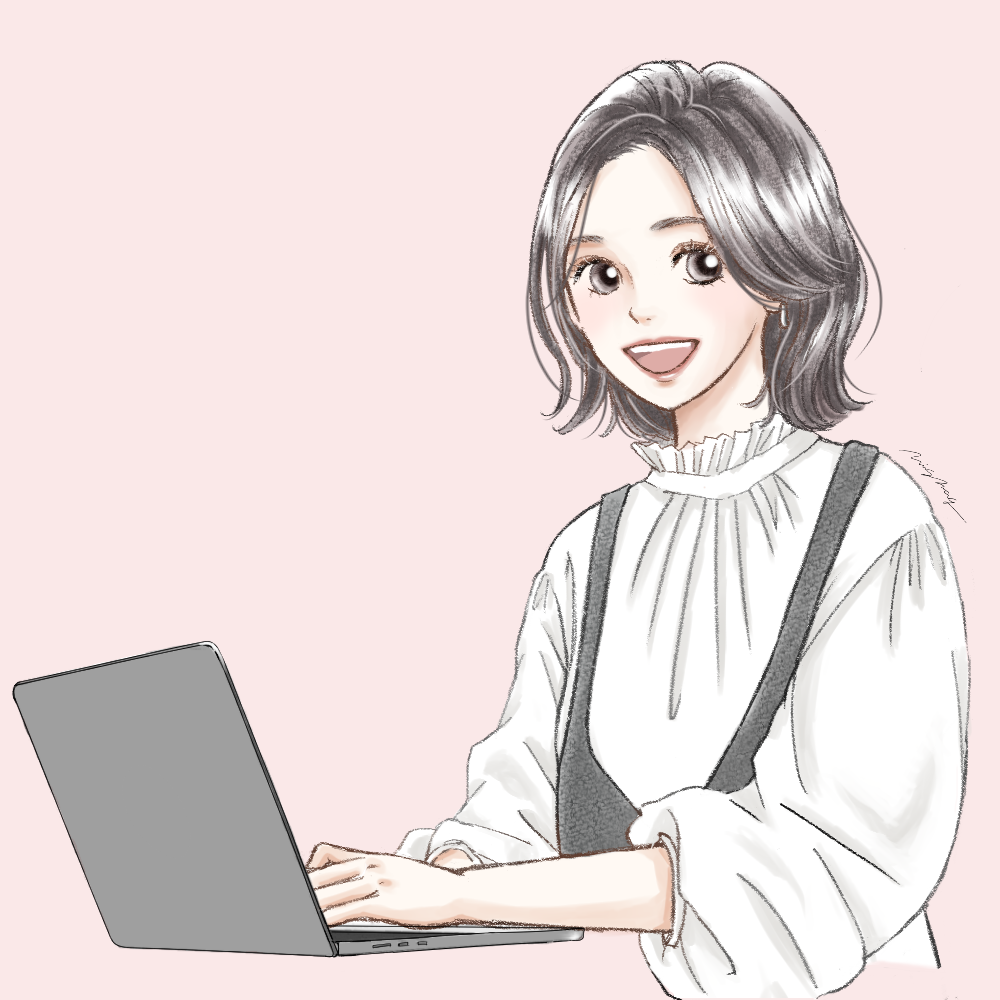
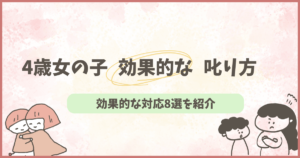

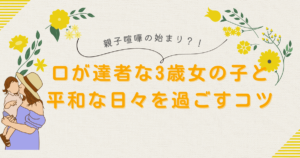
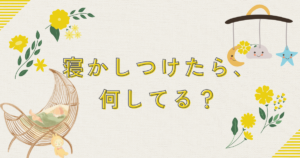
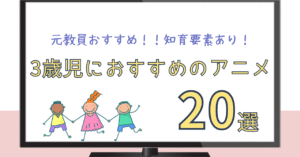
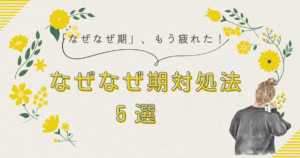
コメント